青年会議
活動報告
Report
2026.01.08
第 44 回全私保連青年会議奄美大会 開催報告
Report
2025.12.05
(公社)京都市保育園連盟青年部の紹介
1 青年部の概要
京都市保育園連盟の青年部運営委員会は、45歳までの後継者候補の先生方が所属する組織です。京都市保育園連盟270か園の加盟園のうち、現在は28人の先生が在籍し、月1回の活動を続けています。
青年部では毎月、京都市連盟理事会での報告を行うほか、固定的な活動テーマを設けず、その時々の部員の興味や関心に応じて意見交換や研修、フィールドワークを行うことが特徴として挙げられます。他の委員会が目的別に設置されている中で、自由に活動できることが青年部ならではの魅力です。
2 過去10年歴代委員長の活動方針
この10年間の最大の試練は新型コロナウイルス感染症の流行でした。活動の多くが制限される中、川島永嗣委員長を中心に、社会全体が接触を制限する方向へ進む中でも「何とか続ける」ことを合言葉に、月1回の青年部活動を継続しました。また、当時はまだ一般的ではなかったオンライン研修の立ち上げにも、技術面で青年部として協力しました。
続く坂口慈孝委員長の時代には、コロナ禍における園運営や行事継続のあり方について、踏み込んだ意見交換を実施。各施設が不安を抱える中で、この場が精神的な支えとなった部員も多くいました。
コロナ禍が明け、矢島敬子委員長の下では「ブランディング」をテーマに活動を展開。ブランディングに力を入れる(株)ジャクエツ本社の見学や、先日ご逝去された社会福祉法人ChaCha Children & Co.の迫田健太郎理事長による研修など、視野を広げる機会を重ねました。
3 現役委員長の展望
そして現在、つないでくださった歴代委員長よりの重いバトンをしっかりと受け継ぎ、後藤洋平委員長の下に学びの機会はもちろん、部員同士の親睦を図る企画を数多く考案しながら活動を行っています。時には京都市を飛び出し、園運営のヒントを求め て全国各地での研修を計画してみたり、部員ごとにチャレンジしてみたい事柄に真剣に向き合ったり、青年世代だからこそできるパワーにアシストしてくれるのが、後藤委員長の持ち味であると言えます。
4 未来の青年部について
京都市保育園連盟青年部では、青年部を代表する実行委員長と、全私保連青年会議幹事役を分担しています。部員人数が多数在籍するからこそ成しえる担当分けなので、利点を活用することは多くの部員に学ぶチャンスを与えていると思います。
これにとどまらず青年部内に活動代表を決めて、各活動に焦点を当てた情報交換も広く深く、分野を問わず活性化するのではないかと考ています。
我々部員たちは仲がよく、プライベートでも交流があり、家族ぐるみでとことん遊びに向き合っています。青年部を卒部された OB の先生方とも継続して交流があります。その根源にあるのは、少年のような遊び心だと思います。好奇心を絶やさずに興味を持って接することは、自園の保育環境の創造に欠かせないエッセンスだと感じます。
これからの部員たちには、青年部の活動を通じて自園の運営のヒントを掴んでもらいたいです。何より、人とつながる素晴らしさと大きな力を感じて、豊かな心を育んでいただきたいです。
次世代育成機関の使命として、互いに高め合える唯一無二の居場所として、青年部ならば頼れると期待され、選んでもらえるように、引き続き努力を重ねて参ります。

鈴鹿サーキット見学研修(2013 年)

定例会後の懇親会にて

(株)ジャクエツ本社見学研修(2024 年)

京都市保育園連盟青年部幹事 石田修一郎先生
(嵯峨野こども園園長)
京都市保育園連盟の青年部運営委員会は、45歳までの後継者候補の先生方が所属する組織です。京都市保育園連盟270か園の加盟園のうち、現在は28人の先生が在籍し、月1回の活動を続けています。
青年部では毎月、京都市連盟理事会での報告を行うほか、固定的な活動テーマを設けず、その時々の部員の興味や関心に応じて意見交換や研修、フィールドワークを行うことが特徴として挙げられます。他の委員会が目的別に設置されている中で、自由に活動できることが青年部ならではの魅力です。
2 過去10年歴代委員長の活動方針
この10年間の最大の試練は新型コロナウイルス感染症の流行でした。活動の多くが制限される中、川島永嗣委員長を中心に、社会全体が接触を制限する方向へ進む中でも「何とか続ける」ことを合言葉に、月1回の青年部活動を継続しました。また、当時はまだ一般的ではなかったオンライン研修の立ち上げにも、技術面で青年部として協力しました。
続く坂口慈孝委員長の時代には、コロナ禍における園運営や行事継続のあり方について、踏み込んだ意見交換を実施。各施設が不安を抱える中で、この場が精神的な支えとなった部員も多くいました。
コロナ禍が明け、矢島敬子委員長の下では「ブランディング」をテーマに活動を展開。ブランディングに力を入れる(株)ジャクエツ本社の見学や、先日ご逝去された社会福祉法人ChaCha Children & Co.の迫田健太郎理事長による研修など、視野を広げる機会を重ねました。
3 現役委員長の展望
そして現在、つないでくださった歴代委員長よりの重いバトンをしっかりと受け継ぎ、後藤洋平委員長の下に学びの機会はもちろん、部員同士の親睦を図る企画を数多く考案しながら活動を行っています。時には京都市を飛び出し、園運営のヒントを求め て全国各地での研修を計画してみたり、部員ごとにチャレンジしてみたい事柄に真剣に向き合ったり、青年世代だからこそできるパワーにアシストしてくれるのが、後藤委員長の持ち味であると言えます。
4 未来の青年部について
京都市保育園連盟青年部では、青年部を代表する実行委員長と、全私保連青年会議幹事役を分担しています。部員人数が多数在籍するからこそ成しえる担当分けなので、利点を活用することは多くの部員に学ぶチャンスを与えていると思います。
これにとどまらず青年部内に活動代表を決めて、各活動に焦点を当てた情報交換も広く深く、分野を問わず活性化するのではないかと考ています。
我々部員たちは仲がよく、プライベートでも交流があり、家族ぐるみでとことん遊びに向き合っています。青年部を卒部された OB の先生方とも継続して交流があります。その根源にあるのは、少年のような遊び心だと思います。好奇心を絶やさずに興味を持って接することは、自園の保育環境の創造に欠かせないエッセンスだと感じます。
これからの部員たちには、青年部の活動を通じて自園の運営のヒントを掴んでもらいたいです。何より、人とつながる素晴らしさと大きな力を感じて、豊かな心を育んでいただきたいです。
次世代育成機関の使命として、互いに高め合える唯一無二の居場所として、青年部ならば頼れると期待され、選んでもらえるように、引き続き努力を重ねて参ります。
(石田修一郎/京都市保育園連盟青年部幹事)

鈴鹿サーキット見学研修(2013 年)

定例会後の懇親会にて

(株)ジャクエツ本社見学研修(2024 年)

京都市保育園連盟青年部幹事 石田修一郎先生
(嵯峨野こども園園長)
Report
2025.11.06
三重県保育青年会の紹介
1 三重県の魅力
三重県は海や山などの自然、長い歴史、豊かな文化が調和した土地です。南北に細長い地形の中に美しい海岸や緑豊かな山々が広がり、季節ごとに違った表情を見せてくれるなど、多様な環境の中には子どもたちの感性を育む題材がたくさんあります。
まず有名なのは伊勢神宮。県の中心的存在である伊勢神宮は2000年以上の歴史を持ち、参道には大きな木々や清らかな川が流れています。昔から「一生に一度はお伊勢さん」と言われ、多くの人が参拝に訪れます。お宮の周りには昔ながらのお店やお菓子屋さんが並び、歩くだけでも心が弾みます。
海沿いの志摩や鳥羽は真珠の養殖や新鮮な海の幸が有名で、海女さんの素潜り実演など、海とと もに暮らす人々の姿に出会えます。入り組んだ海岸線と青い海が広がる英虞湾は真珠の養殖でも有名です。
鈴鹿市には世界的に知られる「鈴鹿サーキット」があり、モータースポーツの聖地として多くの人を魅了しています。家族向けの遊園地やプールもあり子どもたちにも人気です。四日市市はコンビナートの夜景が美しく、ものづくりの町としても発展し、地域の産業を支えています。
そして三重と言えば、食べもののおいしさも魅力の一つ。世界的に知られる松阪牛や、ふっくら柔らかい伊勢うどん、カツオを使った漁師料理・てこね寿司など、どれも地元の人に愛されています。おみやげには、優しい甘さの赤福もオススメです。
歴史、自然、食、産業……と、三重県には日本らしい魅力がぎゅっと詰まっています。
2 三重県保育青年会の歴史
2015(平成27)年に、私立保育園連盟青年部と日本保育協会青年部三重県支部が一つになり、「三重県保育青年会」が新たに生まれました。発足当初から、三重県内各地で研修会や交流会を開催し、遊びや表現活動、子どもの発達、保護者との関わり方などをテーマに語り合ってきました。現在も、青年保育者として必要とされる保育の研鑽および情報交換に努め、児童福祉の増進、保育事業の推進に寄与することを目的として、満50歳までの青年保育者、29人で日々活動しています。
3 三重県保育青年会の活動概要
(1) 青年会組織
会長1名・副会長4名を執行部として、副会長を「全私保連青年会議三重県代表幹事」「日保協青年部三重県支部長」「研修担当」「会計担当」と役割を明確に分けて会の組織基盤を強化し、会員間の結束・情報共有体制・活動の活性化を図っています。
(2) 研修会の開催
年間を通じて、研修会や学習会を企画・開催しています。テーマは多岐にわたり、保育実践や子どもの発達、遊びの工夫、保護者との関わり方、社会情勢と保育の関係など、時代に求められる保育のあり方を学び、実践に活かせる研修、また会員同士の交流を深めるための交流会も開催しています。
(3) 人材確保活動
三重県私立保育連盟とともに、保育士養成校への訪問や就職ガイダンスを開催しています。
(4) 会員間の親睦交流
会員間の交流や情報交換を目的とした親睦交流の場を企画しています。安心して話せる場があることで、日々の悩みや不安も共有でき、仕事への活力につながります。また、三重県私保連の先生方との意見交換も行っています。
4 三重県保育青年会の研修
2024(令和6)年度は、「己書わ楽や道場」上席師範・まちたにやすこ氏をお招きし、子どもたちの自由な想像力や発想力、コミュニケーション能力を育むために職員が心がけるべきことについて講演いただきました。まちたに氏は、己書(おのれしょ)という独自の筆文字表現を通じて、自分の個性を表現することの大切さや、失敗を恐れず自由に描く楽しさを強調されました。参加者一同は、子どもたちの自主性を尊重し、柔軟な発想を促す環境づくりや対話を重視する姿勢の重要性を改めて認識しました。
デジタル園見学として、日保協青年部幼児教育保育委員会委員長・高尾宗宏氏をお招きし、動画を駆使して2園の施設見学を行いました。実際に園に足を運んだかのようなリアルな映像で、園の雰囲気や子どもたちの様子を感じることができ、とても貴重な体験でした。動画の中で、園内で「あるある!」となるシチュエーションをもとに、「自分ならどう対応するだろう?」を参加者で一緒に語るグループワークも行いました。自分たちの園の保育にも活かせるヒントや工夫を持ち帰ることができ、大変有意義な時間となりました。
また実際に石川の地を訪れ、保育施設を訪問し、先生方から地震発生当時の状況や復旧までの歩みを伺いました。限られた環境の中でも、子どもたちの笑顔と日常を守るために尽力されてきた姿に、保育のもつ力と地域とのつながりの大切さを改めて感じました。被災地での経験や工夫は、災害時に子どもを守る備えとして、私たち自身の保育現場にも活かしていきたいと思います。
三重県に限らず、保育環境は少子化や保育ニーズの多様化など、さまざまな変化に直面しています。保育士不足は依然として大きな課題ですが、その中でも子どもたちの健やかな成長を支えるため、現場の保育者は日々努力を重ね、地域や施設ごとの特色を活かした保育実践も進んでいます。
こうした情勢の中、私たち三重県保育青年会は若手保育者がつながり、情報を共有し合うことで、それぞれの悩みや課題を乗り越え、保育の質の向上を目指しています。変化の激しい社会だからこそ、仲間と学び合い、支え合うことが大切です。保育現場で感じる不安や疑問を共有し、前向きに取り組むことで、自信をもって子どもたちに向き合える力を身につけていきたいと考えています。
これからも三重県保育青年会は若手保育者の成長を支え、地域に根ざした保育の質の向上に貢献して参ります。変化の激しい時代だからこそ、ともに学び合い、支え合う絆を大切にしながら、保育の未来を切り拓いていきたいと思います。
多くの皆様のご理解とご協力をいただきながら、これからも一丸となって歩んで参ります。

石川県の保育施設を訪問し、お話を伺う

まちたにやすこ氏による研修

令和7年度第1回研修

令和7年度第2回研修
三重県は海や山などの自然、長い歴史、豊かな文化が調和した土地です。南北に細長い地形の中に美しい海岸や緑豊かな山々が広がり、季節ごとに違った表情を見せてくれるなど、多様な環境の中には子どもたちの感性を育む題材がたくさんあります。
まず有名なのは伊勢神宮。県の中心的存在である伊勢神宮は2000年以上の歴史を持ち、参道には大きな木々や清らかな川が流れています。昔から「一生に一度はお伊勢さん」と言われ、多くの人が参拝に訪れます。お宮の周りには昔ながらのお店やお菓子屋さんが並び、歩くだけでも心が弾みます。
海沿いの志摩や鳥羽は真珠の養殖や新鮮な海の幸が有名で、海女さんの素潜り実演など、海とと もに暮らす人々の姿に出会えます。入り組んだ海岸線と青い海が広がる英虞湾は真珠の養殖でも有名です。
鈴鹿市には世界的に知られる「鈴鹿サーキット」があり、モータースポーツの聖地として多くの人を魅了しています。家族向けの遊園地やプールもあり子どもたちにも人気です。四日市市はコンビナートの夜景が美しく、ものづくりの町としても発展し、地域の産業を支えています。
そして三重と言えば、食べもののおいしさも魅力の一つ。世界的に知られる松阪牛や、ふっくら柔らかい伊勢うどん、カツオを使った漁師料理・てこね寿司など、どれも地元の人に愛されています。おみやげには、優しい甘さの赤福もオススメです。
歴史、自然、食、産業……と、三重県には日本らしい魅力がぎゅっと詰まっています。
2 三重県保育青年会の歴史
2015(平成27)年に、私立保育園連盟青年部と日本保育協会青年部三重県支部が一つになり、「三重県保育青年会」が新たに生まれました。発足当初から、三重県内各地で研修会や交流会を開催し、遊びや表現活動、子どもの発達、保護者との関わり方などをテーマに語り合ってきました。現在も、青年保育者として必要とされる保育の研鑽および情報交換に努め、児童福祉の増進、保育事業の推進に寄与することを目的として、満50歳までの青年保育者、29人で日々活動しています。
3 三重県保育青年会の活動概要
(1) 青年会組織
会長1名・副会長4名を執行部として、副会長を「全私保連青年会議三重県代表幹事」「日保協青年部三重県支部長」「研修担当」「会計担当」と役割を明確に分けて会の組織基盤を強化し、会員間の結束・情報共有体制・活動の活性化を図っています。
(2) 研修会の開催
年間を通じて、研修会や学習会を企画・開催しています。テーマは多岐にわたり、保育実践や子どもの発達、遊びの工夫、保護者との関わり方、社会情勢と保育の関係など、時代に求められる保育のあり方を学び、実践に活かせる研修、また会員同士の交流を深めるための交流会も開催しています。
(3) 人材確保活動
三重県私立保育連盟とともに、保育士養成校への訪問や就職ガイダンスを開催しています。
(4) 会員間の親睦交流
会員間の交流や情報交換を目的とした親睦交流の場を企画しています。安心して話せる場があることで、日々の悩みや不安も共有でき、仕事への活力につながります。また、三重県私保連の先生方との意見交換も行っています。
4 三重県保育青年会の研修
2024(令和6)年度は、「己書わ楽や道場」上席師範・まちたにやすこ氏をお招きし、子どもたちの自由な想像力や発想力、コミュニケーション能力を育むために職員が心がけるべきことについて講演いただきました。まちたに氏は、己書(おのれしょ)という独自の筆文字表現を通じて、自分の個性を表現することの大切さや、失敗を恐れず自由に描く楽しさを強調されました。参加者一同は、子どもたちの自主性を尊重し、柔軟な発想を促す環境づくりや対話を重視する姿勢の重要性を改めて認識しました。
デジタル園見学として、日保協青年部幼児教育保育委員会委員長・高尾宗宏氏をお招きし、動画を駆使して2園の施設見学を行いました。実際に園に足を運んだかのようなリアルな映像で、園の雰囲気や子どもたちの様子を感じることができ、とても貴重な体験でした。動画の中で、園内で「あるある!」となるシチュエーションをもとに、「自分ならどう対応するだろう?」を参加者で一緒に語るグループワークも行いました。自分たちの園の保育にも活かせるヒントや工夫を持ち帰ることができ、大変有意義な時間となりました。
また実際に石川の地を訪れ、保育施設を訪問し、先生方から地震発生当時の状況や復旧までの歩みを伺いました。限られた環境の中でも、子どもたちの笑顔と日常を守るために尽力されてきた姿に、保育のもつ力と地域とのつながりの大切さを改めて感じました。被災地での経験や工夫は、災害時に子どもを守る備えとして、私たち自身の保育現場にも活かしていきたいと思います。
三重県に限らず、保育環境は少子化や保育ニーズの多様化など、さまざまな変化に直面しています。保育士不足は依然として大きな課題ですが、その中でも子どもたちの健やかな成長を支えるため、現場の保育者は日々努力を重ね、地域や施設ごとの特色を活かした保育実践も進んでいます。
こうした情勢の中、私たち三重県保育青年会は若手保育者がつながり、情報を共有し合うことで、それぞれの悩みや課題を乗り越え、保育の質の向上を目指しています。変化の激しい社会だからこそ、仲間と学び合い、支え合うことが大切です。保育現場で感じる不安や疑問を共有し、前向きに取り組むことで、自信をもって子どもたちに向き合える力を身につけていきたいと考えています。
これからも三重県保育青年会は若手保育者の成長を支え、地域に根ざした保育の質の向上に貢献して参ります。変化の激しい時代だからこそ、ともに学び合い、支え合う絆を大切にしながら、保育の未来を切り拓いていきたいと思います。
多くの皆様のご理解とご協力をいただきながら、これからも一丸となって歩んで参ります。
(小野寺真志/三重県保育青年会副会長、くすのき保育園園長)

石川県の保育施設を訪問し、お話を伺う

まちたにやすこ氏による研修

令和7年度第1回研修

令和7年度第2回研修
Report
2025.10.06
第2回全国私立保育連盟青年会議・日本保育協会青年部合同研修会 in 大阪
7月29日、大阪市・TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋にて、2回目となる全私保連青年会議・日保協青年部合同研修会が開催されました。昨年度、能登半島地震の復興支援を目的としたチャリティー研修会として石川県金沢市で初開催された本研修会。多くの参加者から高い評価と、開催の継続を望む声をいただき、今年度も大阪の地で再び実現することができました。「ともに学び、ともに支える─ひとつになる支援」をテーマに掲げ、団体の垣根を越えて、全国各地から150人を超える保育関係者が足を運んでくださり、会場は昨年同様の熱気と期待に包まれていました。参加者の顔ぶれは、園長や次世代の経営層、現場の中心を担う若手リーダーなど多岐にわたり、保育の未来を見据えた真剣な学びの場となりました。
最初の講演は、(株)福祉総研上席研究員・松本和也氏による「新しい処遇改善の留意点」についてのお話でした。
松本氏は、保育士の処遇改善が近年どのように制度化されてきたのか、その背景と今後の見通しについて、具体的なデータとともに解説してくださいました。特に、処遇改善加算の制度設計における課題や現場での運用上の注意点は、参加者にとって非常にわかりやすく実践的で、大変参考になる内容でした。人材育成と処遇改善をどのように結びつけていくかについても言及があり、今後の園運営に直結する示唆を与えていただきました。
会場では、熱心にメモを取る姿が見られ、講演後には「もっと時間がほしかった」「さらに深いところまで聞きたかった」などの声が相次ぎ、個別に質問に行く参加者も多く見られました。今回の処遇改善加算の変更に対する関心の高さが如実に現われている光景でした。
続いては滋賀大学准教授・山本一成氏により、「生きているものどうしの想像力─保育が紡ぐサステナビリティ」というテーマで2つ目の講演が行われました。
山本氏は、持続可能な社会における保育の意義を、哲学的かつ具体的に語ってくださいました。子どもを「未来の担い手」ではなく「今を生きる存在」として捉え、その感性や想像力を尊重する保育のあり方が、社会全体のサステナビリティにつながるという視点は、多くの参加者の心に深く響いたのではないかと感じました。また、自然との関わり、命との向き合い方をどのように保育の中で伝えていくかというテーマは、日々の実践に直結する問いかけでもありました。
質疑応答の時間も設けてくださり、参加者との活発な意見交換が行われ、こちらもまさに「時間が足りない」と感じられるほど濃密な学びの時間となりました。園長や経営層はもとより、現場で子どもたちと向き合っている保育士の方々にとって、新しい気づきにたくさん出会えた講演でした。
研修終了後には情報交換会が開かれ、講師の方も含め、およそ100人が参加しました。会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、所属団体や地域の違いを越えて交流が広がりました。ここでは、研修内容を踏まえた意見の交換や、それぞれの園で抱える課題の共有が活発に行われ、参加者同士の未来につながる出会いや、貴重な関係性を構築する機会となりました。会の途中では、両団体の役員や諸先輩方からも温かい激励の言葉が寄せられ、我々青年世代が今後さらに力を合わせて歩んでいくことへの期待を改めて痛感しました。
① 保育制度の最新情報と現場実践の結びつき
松本氏の講演を通じ、処遇改善制度に関する最新の知識を得るとともに、それをどのように園運営へ生かすかの具体的視点を学ぶことができました。
② 保育の理念的深化と社会的役割の再確認
山本氏の講演を通じ、保育が単なる子育て支援にとどまらず、社会の持続可能性を支える重要な営みであることを再確認できました。
③ 全国規模のネットワークの強化
情報交換会を含め、参加者同士が地域、団体の垣根を越えて学び合い、次回以降にもつながる連携の芽が育まれました。
一方で、今後の課題も浮き彫りになりました。まずは、両講演が大変好評であった反面、「もっと聞きたい」「質問できる時間が短い」という声が寄せられました。今後の研修設計においては、講師と参加者がより双方向にコミュニケーションをとれる仕組みを検討する必要があると感じます。また、150人を上回るという参加規模を受け、運営体制のさらなる強化や、参加者の多様なニーズに応じたプログラム編成も今後の検討課題と言えます。
そのような課題が明らかになったことも含めて、今回の合同研修会の成果だと思っています。これからも、青年世代が中心となって保育界全体を盛り上げていけるよう努力していきたいと思います。
今回の研修会を支えてくださったすべての方々、そしてともに学び合った仲間に心より感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました。

日保協青年部・中西淳也部長

講演中の松本和也氏

講演中の山本一成氏

研修会の様子

日保協・吉田 学理事長

全私保連青年会議・伊藤 悟会長
* * *
開会にあたり、日保協青年部長の中西淳也氏より挨拶がありました。子どもたちの最善の利益を第一に考える姿勢を共有しつつ、2回目の合同研修を迎えることができたことへの感謝が述べられ、さらに、この研修が単なる学びの場にとどまらず、参加者一人一人が地域や現場に持ち帰って実践してほしい旨が強調されました。最初の講演は、(株)福祉総研上席研究員・松本和也氏による「新しい処遇改善の留意点」についてのお話でした。
松本氏は、保育士の処遇改善が近年どのように制度化されてきたのか、その背景と今後の見通しについて、具体的なデータとともに解説してくださいました。特に、処遇改善加算の制度設計における課題や現場での運用上の注意点は、参加者にとって非常にわかりやすく実践的で、大変参考になる内容でした。人材育成と処遇改善をどのように結びつけていくかについても言及があり、今後の園運営に直結する示唆を与えていただきました。
会場では、熱心にメモを取る姿が見られ、講演後には「もっと時間がほしかった」「さらに深いところまで聞きたかった」などの声が相次ぎ、個別に質問に行く参加者も多く見られました。今回の処遇改善加算の変更に対する関心の高さが如実に現われている光景でした。
続いては滋賀大学准教授・山本一成氏により、「生きているものどうしの想像力─保育が紡ぐサステナビリティ」というテーマで2つ目の講演が行われました。
山本氏は、持続可能な社会における保育の意義を、哲学的かつ具体的に語ってくださいました。子どもを「未来の担い手」ではなく「今を生きる存在」として捉え、その感性や想像力を尊重する保育のあり方が、社会全体のサステナビリティにつながるという視点は、多くの参加者の心に深く響いたのではないかと感じました。また、自然との関わり、命との向き合い方をどのように保育の中で伝えていくかというテーマは、日々の実践に直結する問いかけでもありました。
質疑応答の時間も設けてくださり、参加者との活発な意見交換が行われ、こちらもまさに「時間が足りない」と感じられるほど濃密な学びの時間となりました。園長や経営層はもとより、現場で子どもたちと向き合っている保育士の方々にとって、新しい気づきにたくさん出会えた講演でした。
研修終了後には情報交換会が開かれ、講師の方も含め、およそ100人が参加しました。会場は終始和やかな雰囲気に包まれ、所属団体や地域の違いを越えて交流が広がりました。ここでは、研修内容を踏まえた意見の交換や、それぞれの園で抱える課題の共有が活発に行われ、参加者同士の未来につながる出会いや、貴重な関係性を構築する機会となりました。会の途中では、両団体の役員や諸先輩方からも温かい激励の言葉が寄せられ、我々青年世代が今後さらに力を合わせて歩んでいくことへの期待を改めて痛感しました。
* * *
本研修会を通じて得られた成果を大きく3点にまとめます。① 保育制度の最新情報と現場実践の結びつき
松本氏の講演を通じ、処遇改善制度に関する最新の知識を得るとともに、それをどのように園運営へ生かすかの具体的視点を学ぶことができました。
② 保育の理念的深化と社会的役割の再確認
山本氏の講演を通じ、保育が単なる子育て支援にとどまらず、社会の持続可能性を支える重要な営みであることを再確認できました。
③ 全国規模のネットワークの強化
情報交換会を含め、参加者同士が地域、団体の垣根を越えて学び合い、次回以降にもつながる連携の芽が育まれました。
一方で、今後の課題も浮き彫りになりました。まずは、両講演が大変好評であった反面、「もっと聞きたい」「質問できる時間が短い」という声が寄せられました。今後の研修設計においては、講師と参加者がより双方向にコミュニケーションをとれる仕組みを検討する必要があると感じます。また、150人を上回るという参加規模を受け、運営体制のさらなる強化や、参加者の多様なニーズに応じたプログラム編成も今後の検討課題と言えます。
そのような課題が明らかになったことも含めて、今回の合同研修会の成果だと思っています。これからも、青年世代が中心となって保育界全体を盛り上げていけるよう努力していきたいと思います。
今回の研修会を支えてくださったすべての方々、そしてともに学び合った仲間に心より感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました。
(伊藤 悟/全私保連青年会議会長)

日保協青年部・中西淳也部長

講演中の松本和也氏

講演中の山本一成氏

研修会の様子

日保協・吉田 学理事長

全私保連青年会議・伊藤 悟会長
Report
2025.09.05
神戸市私立保育園連盟青年会議の紹介
1 神戸市の魅力
神戸市は人口約150万人を擁し、政令指定都市として全国第7位に位置する都市です。海と山に囲まれた美しい自然環境と、異国情緒あふれる街並みが調和した魅力的な都市でもあり、国内外から多くの人々を引きつけています。1868年の開港以来、多くの外国文化が流入し、北野異人館街や旧居留地など独自の歴史的景観が形成されました。こうした異文化が息づく街並みは、訪れる人々に新鮮な印象と深い感動を与えてくれます。
また神戸は“グルメの街”としても広く知られ、世界的に有名な神戸牛をはじめ、スイーツ、ベーカリー、中華街・南京町の本格中華など、多彩な食文化が楽しめます。近年ではウォーターフロントエリアの再開発も進み、リニューアルされた神戸ポートタワー、芸術と水族館が融合した神戸ポートミュージアム、音楽とスポーツが融合したジーライオンアリーナ神戸など、新たな観光スポットも登場しています。ハーバーランドやメリケンパークでは、海風を感じながらの散策や夜景鑑賞も楽しめるなど、心身ともにリフレッシュできる場所として人気です。
ぜひ、神戸の魅力を感じにお越しください。
2 青年会議の目的および事業
(公社)神戸市私立保育園連盟青年会議は、加盟園の経営や運営の次代を担う園長や職員が相互に研鑽と親睦を深めることを目的として活動しています。その目的達成のため、神戸市私保連の事業に積極的に参画し、研修の企画・実施を行っています。また、神戸市私立幼稚園連盟次世代部会とも定期的に交流し、神戸市の保育・教育の未来について、意見交換を行う場を設けています。保育園、こども園、幼稚園といった施設の枠を超え 、「子どもたちのために何ができるか」「保育士・幼稚園教諭の魅力を発信するにはどうすればよいか 」といった問いに対して、青年らしく多様な視点で意見を交わしながら活動を進めています。
現在の会員数は30人ですが、今後はより多くの若手職員にも参画してもらい、神戸市における保育のさらなる発展と地域社会の子育て支援の充実に貢献していきたいと考えています。また、地域とのつながりを大切にしながら、現場のニーズに即した活動を通して、未来の保育を支える人材の育成にも力を注いで参ります。
3 青年会議の研修
青年会議では、会長、副会長、部会長を中心に研修内容や学びの方向性について意見を出し合い、 実りある研修を企画しています。主に3つの柱からなる研修を展開しています。
1つ目は「視察研修」です。保育園やこども園に加え、児童養護施設や介護付きシェアハウスなど、福祉の幅広い分野に触れる視察を行っています。視察研修は、保育の質を向上させるうえで非常に貴重な学びの場です。他園の保育プログラムや実践を知ることで、自園の保育に新たな視点やヒントが得られます。遊びの工夫や発達に応じた支援方法、施設環境の整備、職員間の連携のあり方など、多くの気づきがあります。他園の良い点を実際に見て学ぶことで具体的な改善にもつながり、結果として地域全体の保育水準の向上に貢献しています。
2つ目は「職員(現場)向け研修」です。これまでに、運動遊び、絵画技法、アンガーマネジメントなど、子どもの育ちに直結する内容を取り上げてきました。令和6年度は助産師の方を講師に迎え、命の尊さや出産の奇跡、そして出生後の支援について学び、保育の原点を見つめ直す機会となりました。経営面だけでなく、日々子どもと関わる現場の職員が深く学ぶことで、子どもに寄り添った保育実践が可能になります。令和7年度は、より多くの職員が積極的に研修に参加し、自園で実践できる学びを深められるよう努めて参ります。今後も実践的かつ継続的な研修を通じて、保育の質を高めていきたいと考えています。
3つ目は「経営層向け研修」です。社会福祉法人の経営のあり方や、今後の保育経営について学ぶ場を設けています。令和6年度は「園の魅力発信」をテーマに、SNSを活用したブランディングや情報発信について学びました。園によってSNSの目的や手法は異なりますが、情報発信の重要性が高まる中で、採用活動や園児募集にも直結するテーマとして活発な意見交換が行われました。会員同士の交流を通じて新たな視点を得るとともに、判断力・実践力の向上にもつながる有意義な研修となりました。
4 青年会議のこれから
私たち若手経営者は、今まさに保育の未来を左右する転換点に立っています。少子化の加速、保育 士不足、保護者ニーズの多様化、ICTの進展など、保育を取り巻く環境は急速に変化しています。その中で経営の手法も保育のあり方も、従来の常識にとらわれない柔軟な視点と発想が求められています。
単に施設を運営するという視点ではなく、「子ども・保護者・職員・地域社会」すべてに目を向け、社会全体で子どもを育てるという意識が必要だと考えています。今「こどもまんなか社会」という考え方が掲げられていますが、私たちはまさにその実現を目指し、子どもたちの「やってみたい」「知りたい」「関わりたい」という意欲を大切にして主体的に学べる環境づくりを進めていく必要があります。青年会議では、保育の質の向上と、それを支える経営の質の向上という“両輪”のバランスを重視しながら、研修や意見交換を活発に行い、多様な価値観を学び合うことで、地域社会に貢献していきたいと考えています。今後も新しい課題に果敢に挑戦し、柔軟で創造的な取り組みを進めて参ります。
最後に、先輩方が神戸の保育を長年築き上げてこられた成果として、2024年の「共働き子育てしやすい街ランキング」で全国第1位を獲得しました。私たち青年も先輩方の想いをしっかりと受け継いでいかなければなりません。神戸市の子育て支援のさらなる充実に貢献できるよう、熱意をもって活動して参ります。今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。

青年会議総会の様子

保育園の視察研修

多世代型介護付きシェアハウスの視察研修

令和7年度全国保育協議会
近畿ブロック保育研究集会
神戸大会の様子(2025年7月10日)
神戸市は人口約150万人を擁し、政令指定都市として全国第7位に位置する都市です。海と山に囲まれた美しい自然環境と、異国情緒あふれる街並みが調和した魅力的な都市でもあり、国内外から多くの人々を引きつけています。1868年の開港以来、多くの外国文化が流入し、北野異人館街や旧居留地など独自の歴史的景観が形成されました。こうした異文化が息づく街並みは、訪れる人々に新鮮な印象と深い感動を与えてくれます。
また神戸は“グルメの街”としても広く知られ、世界的に有名な神戸牛をはじめ、スイーツ、ベーカリー、中華街・南京町の本格中華など、多彩な食文化が楽しめます。近年ではウォーターフロントエリアの再開発も進み、リニューアルされた神戸ポートタワー、芸術と水族館が融合した神戸ポートミュージアム、音楽とスポーツが融合したジーライオンアリーナ神戸など、新たな観光スポットも登場しています。ハーバーランドやメリケンパークでは、海風を感じながらの散策や夜景鑑賞も楽しめるなど、心身ともにリフレッシュできる場所として人気です。
ぜひ、神戸の魅力を感じにお越しください。
2 青年会議の目的および事業
(公社)神戸市私立保育園連盟青年会議は、加盟園の経営や運営の次代を担う園長や職員が相互に研鑽と親睦を深めることを目的として活動しています。その目的達成のため、神戸市私保連の事業に積極的に参画し、研修の企画・実施を行っています。また、神戸市私立幼稚園連盟次世代部会とも定期的に交流し、神戸市の保育・教育の未来について、意見交換を行う場を設けています。保育園、こども園、幼稚園といった施設の枠を超え 、「子どもたちのために何ができるか」「保育士・幼稚園教諭の魅力を発信するにはどうすればよいか 」といった問いに対して、青年らしく多様な視点で意見を交わしながら活動を進めています。
現在の会員数は30人ですが、今後はより多くの若手職員にも参画してもらい、神戸市における保育のさらなる発展と地域社会の子育て支援の充実に貢献していきたいと考えています。また、地域とのつながりを大切にしながら、現場のニーズに即した活動を通して、未来の保育を支える人材の育成にも力を注いで参ります。
3 青年会議の研修
青年会議では、会長、副会長、部会長を中心に研修内容や学びの方向性について意見を出し合い、 実りある研修を企画しています。主に3つの柱からなる研修を展開しています。
1つ目は「視察研修」です。保育園やこども園に加え、児童養護施設や介護付きシェアハウスなど、福祉の幅広い分野に触れる視察を行っています。視察研修は、保育の質を向上させるうえで非常に貴重な学びの場です。他園の保育プログラムや実践を知ることで、自園の保育に新たな視点やヒントが得られます。遊びの工夫や発達に応じた支援方法、施設環境の整備、職員間の連携のあり方など、多くの気づきがあります。他園の良い点を実際に見て学ぶことで具体的な改善にもつながり、結果として地域全体の保育水準の向上に貢献しています。
2つ目は「職員(現場)向け研修」です。これまでに、運動遊び、絵画技法、アンガーマネジメントなど、子どもの育ちに直結する内容を取り上げてきました。令和6年度は助産師の方を講師に迎え、命の尊さや出産の奇跡、そして出生後の支援について学び、保育の原点を見つめ直す機会となりました。経営面だけでなく、日々子どもと関わる現場の職員が深く学ぶことで、子どもに寄り添った保育実践が可能になります。令和7年度は、より多くの職員が積極的に研修に参加し、自園で実践できる学びを深められるよう努めて参ります。今後も実践的かつ継続的な研修を通じて、保育の質を高めていきたいと考えています。
3つ目は「経営層向け研修」です。社会福祉法人の経営のあり方や、今後の保育経営について学ぶ場を設けています。令和6年度は「園の魅力発信」をテーマに、SNSを活用したブランディングや情報発信について学びました。園によってSNSの目的や手法は異なりますが、情報発信の重要性が高まる中で、採用活動や園児募集にも直結するテーマとして活発な意見交換が行われました。会員同士の交流を通じて新たな視点を得るとともに、判断力・実践力の向上にもつながる有意義な研修となりました。
4 青年会議のこれから
私たち若手経営者は、今まさに保育の未来を左右する転換点に立っています。少子化の加速、保育 士不足、保護者ニーズの多様化、ICTの進展など、保育を取り巻く環境は急速に変化しています。その中で経営の手法も保育のあり方も、従来の常識にとらわれない柔軟な視点と発想が求められています。
単に施設を運営するという視点ではなく、「子ども・保護者・職員・地域社会」すべてに目を向け、社会全体で子どもを育てるという意識が必要だと考えています。今「こどもまんなか社会」という考え方が掲げられていますが、私たちはまさにその実現を目指し、子どもたちの「やってみたい」「知りたい」「関わりたい」という意欲を大切にして主体的に学べる環境づくりを進めていく必要があります。青年会議では、保育の質の向上と、それを支える経営の質の向上という“両輪”のバランスを重視しながら、研修や意見交換を活発に行い、多様な価値観を学び合うことで、地域社会に貢献していきたいと考えています。今後も新しい課題に果敢に挑戦し、柔軟で創造的な取り組みを進めて参ります。
最後に、先輩方が神戸の保育を長年築き上げてこられた成果として、2024年の「共働き子育てしやすい街ランキング」で全国第1位を獲得しました。私たち青年も先輩方の想いをしっかりと受け継いでいかなければなりません。神戸市の子育て支援のさらなる充実に貢献できるよう、熱意をもって活動して参ります。今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
(橋本拓弥/神戸市私立保育園連盟青年会議会長、幼保連携型認定こども園光愛児園副園長)

青年会議総会の様子

保育園の視察研修

多世代型介護付きシェアハウスの視察研修

令和7年度全国保育協議会
近畿ブロック保育研究集会
神戸大会の様子(2025年7月10日)
Report
2025.08.05
宮崎県保育連盟連合会青年部の紹介
1 青年部の歩み
(一社)宮崎県保育連盟連合会青年部は、2005年(平成17)年に私立保育園連盟青年部「若潮会」と日本保育協会青年部宮崎県支部が一つになり、新しく生まれ変わりました。両団体とも民間保育園の若手が保育園の充実を通して、子どもたちの健やかな成長を願い、寄与することを目的として活動していたので、そのまま引き継ぐ形で現在に至っています。
宮崎県保育連盟連合会に加盟する満45歳以下の青年保育者が部員の対象となり、令和7年度現在、部員29人、賛助部員53人の計82人の部員数で構成し、青年部の仲間とともに学び合い、語り合い、互いに助け合える組織として取り組んでいます。
2 青年部の活動内容
青年部は、青年部員としての特性を発揮し、保育事業全般に関する研究調査や研修等により、施設 運営の専門性の向上を図り部員相互の資質を高めることとして、活動内容は以下の通りとなっています 。
(1)部員間で資質向上を目指す情報交換および情報発信を促進するための事業
(2)部員および県保連加盟園への研修、および研究調査に関する事業
(3)県保連および上部各団体との連絡協調に関する事業
(4)その他、目的達成のために必要な事業
「こども家庭庁」の創設から早2年が経ち、令和 7年度よりさらに「こども・子育て支援」に関する内容の充実が図られています。しかしながら、保育現場の現状を見てみると、保育の質の向上に向けた人材確保、処遇改善、少子化など、さまざまな課題が散見されています。
■子どもたち、職員を守っていくために、何ができるか
我々青年部としても、これからの園を守っていく者として、さまざまな課題の本質を捉え、思考し、対話し、行動していくことが大切なことと考え、常に前を向き進んでいく青年部でありたいという思いを抱き、活動しています。
青年部主催の研修においては、年に約3回の活動をしており、その時々の保育に関わる情勢の動向、また部員の疑問や課題感を汲み取り、運営委員会で協議し、企画立案をしています。ここ数年においては、人口減少時代における運営や組織マネジメント、保育制度の変遷における持続可能な園運営の戦略、災害時代を生き抜くための安全管理など、さまざまな角度から教育・保育に必要となる研修を行っています。
また、青年部のみの研修だけではなく、特に九州内の青年部組織との合同研修や施設見学、意見交換なども積極的に行い、情報の共有と研鑽に努めているところです。
そして、不定期ではありますが、「青年部だより」の発行も行っており、青年部活動を広く知っていただくための活動もしています。
3 第 40 回全国私立保育連盟青年会議宮崎大会の開催
2019(令和元)年に、翌年2020(令和2)年開催の全国大会のお話をいただきました。
その当時の青年部の中で、「宮崎の青年部で全国大会をつくり上げることができるのだろうか」と、非常に動揺したことを今でも覚えています。そのような気持ちもありながらではありましたが、お引き受けし、大会の成功に向けて、鋭意準備を進めていました。
■その最中、新型コロナウイルス感染症という未曾有の感染症が拡大
これまで築かれてきた青年会議全国大会の歴史 をどうしたら紡いでいけるのか……。
全私保連並びに青年会議の先生方、宮崎県青年部内で協議を重ねる中で、一時は中止という話も出ましたが、どのような形でも開催したいという思いをお伝えしたところ、1年延期となり、またWEB方式での全国大会という新たな形として開催を実現することができました。
宮崎大会の開催に関わっていただいたすべての皆様には、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。このような経験をしたからこそ青年部の結束力が高まったことは言うまでもなく、その後の青年部活動が活性化する非常に大きなきっかけとなりました。
4 青年部のこれから
青年会議全国大会開催という非常に貴重な経験、研修や意見交換を通して成長している青年部です。今後も、既述の通り、子どもたちの健やかな成長を守っていくことはもちろんのこと、職員をはじめとする園運営に携わる人や事柄をしっかりと見つめ、常に前を向き、進んでいきたいと考えます。
これからも宮崎県内各地の先生方と連携し、また全国の先生方とつながっていく中で、宮崎県保育連盟連合会青年部がますます盛り上がりを見せ、飛躍していけますよう『勇往邁進(ゆうおうまいしん)』して参ります。

青年会議宮崎大会・現地調査(2021年)

青年会議宮崎大会・実行委員会のメンバー(2021年)

チームビルディング研修(2022年)

保育制度研修(2025年)

鹿児島市保育園協会青年部との 2組織合同研修(2024年)

鹿児島市保育園協会青年部との 2組織合同研修(2024年)
(一社)宮崎県保育連盟連合会青年部は、2005年(平成17)年に私立保育園連盟青年部「若潮会」と日本保育協会青年部宮崎県支部が一つになり、新しく生まれ変わりました。両団体とも民間保育園の若手が保育園の充実を通して、子どもたちの健やかな成長を願い、寄与することを目的として活動していたので、そのまま引き継ぐ形で現在に至っています。
宮崎県保育連盟連合会に加盟する満45歳以下の青年保育者が部員の対象となり、令和7年度現在、部員29人、賛助部員53人の計82人の部員数で構成し、青年部の仲間とともに学び合い、語り合い、互いに助け合える組織として取り組んでいます。
2 青年部の活動内容
青年部は、青年部員としての特性を発揮し、保育事業全般に関する研究調査や研修等により、施設 運営の専門性の向上を図り部員相互の資質を高めることとして、活動内容は以下の通りとなっています 。
(1)部員間で資質向上を目指す情報交換および情報発信を促進するための事業
(2)部員および県保連加盟園への研修、および研究調査に関する事業
(3)県保連および上部各団体との連絡協調に関する事業
(4)その他、目的達成のために必要な事業
「こども家庭庁」の創設から早2年が経ち、令和 7年度よりさらに「こども・子育て支援」に関する内容の充実が図られています。しかしながら、保育現場の現状を見てみると、保育の質の向上に向けた人材確保、処遇改善、少子化など、さまざまな課題が散見されています。
■子どもたち、職員を守っていくために、何ができるか
我々青年部としても、これからの園を守っていく者として、さまざまな課題の本質を捉え、思考し、対話し、行動していくことが大切なことと考え、常に前を向き進んでいく青年部でありたいという思いを抱き、活動しています。
青年部主催の研修においては、年に約3回の活動をしており、その時々の保育に関わる情勢の動向、また部員の疑問や課題感を汲み取り、運営委員会で協議し、企画立案をしています。ここ数年においては、人口減少時代における運営や組織マネジメント、保育制度の変遷における持続可能な園運営の戦略、災害時代を生き抜くための安全管理など、さまざまな角度から教育・保育に必要となる研修を行っています。
また、青年部のみの研修だけではなく、特に九州内の青年部組織との合同研修や施設見学、意見交換なども積極的に行い、情報の共有と研鑽に努めているところです。
そして、不定期ではありますが、「青年部だより」の発行も行っており、青年部活動を広く知っていただくための活動もしています。
3 第 40 回全国私立保育連盟青年会議宮崎大会の開催
2019(令和元)年に、翌年2020(令和2)年開催の全国大会のお話をいただきました。
その当時の青年部の中で、「宮崎の青年部で全国大会をつくり上げることができるのだろうか」と、非常に動揺したことを今でも覚えています。そのような気持ちもありながらではありましたが、お引き受けし、大会の成功に向けて、鋭意準備を進めていました。
■その最中、新型コロナウイルス感染症という未曾有の感染症が拡大
これまで築かれてきた青年会議全国大会の歴史 をどうしたら紡いでいけるのか……。
全私保連並びに青年会議の先生方、宮崎県青年部内で協議を重ねる中で、一時は中止という話も出ましたが、どのような形でも開催したいという思いをお伝えしたところ、1年延期となり、またWEB方式での全国大会という新たな形として開催を実現することができました。
宮崎大会の開催に関わっていただいたすべての皆様には、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。このような経験をしたからこそ青年部の結束力が高まったことは言うまでもなく、その後の青年部活動が活性化する非常に大きなきっかけとなりました。
4 青年部のこれから
青年会議全国大会開催という非常に貴重な経験、研修や意見交換を通して成長している青年部です。今後も、既述の通り、子どもたちの健やかな成長を守っていくことはもちろんのこと、職員をはじめとする園運営に携わる人や事柄をしっかりと見つめ、常に前を向き、進んでいきたいと考えます。
これからも宮崎県内各地の先生方と連携し、また全国の先生方とつながっていく中で、宮崎県保育連盟連合会青年部がますます盛り上がりを見せ、飛躍していけますよう『勇往邁進(ゆうおうまいしん)』して参ります。
(徳重亮太/宮崎県保育連盟連合会青年部部長、花笑みすずらんこども園園長)

青年会議宮崎大会・現地調査(2021年)

青年会議宮崎大会・実行委員会のメンバー(2021年)

チームビルディング研修(2022年)

保育制度研修(2025年)

鹿児島市保育園協会青年部との 2組織合同研修(2024年)

鹿児島市保育園協会青年部との 2組織合同研修(2024年)
Report
2025.07.07
兵庫県保育協会青年保育者部会の紹介
1 兵庫県保育協会青年保育者部会の歴史
兵庫県保育協会青年保育者部会は、1984(昭和59)年に「青年保育者会」として発足しました。発足以降、先輩方が会議や勉強会、研修会を開催し、脈々と続いていましたが、2013(平成25)年に兵庫県保育協会が公益法人を設立した折に「青年保育者部会」と改称しました。部会となったことで、兵庫県保育協会の内部組織としての位置づけがより明確になり、活動の幅が広がりました。
発足当初より保育事業後継者の研鑽と相互の連絡協議等の活動を行うという目的で設立をされましたが、現在も青年保育者の資質向上に関する研修会の開催、会員相互の親睦や協調を密にできるような活動を行いながら若手らしい研修会も模索し、より活発な活動ができるような取り組みを考えています。
2 青年保育者部会の活動について
現在、部会長、副部会長、事務局長を中心に幹事会を開催し、青年保育者部会で行う研修会や勉強会の開催に向けての準備を行っています。また2か月に1回、定例会を開催し、会員同士の情報交流や研修会へ向けての協議を行っています。
現在の会員数が20名ほどですので、今後の活動 のためにも、会員が増えることを目指した広報活動を行う必要があると考えています。また、会員向けの研修会だけではなく、兵庫県の保育・子育て環境が充実していくような研修会も積極的に開催していきたいと思っています。
3 青年保育者部会の研修
毎年、さまざまな研修会の企画・運営を行っています。青年保育者部会らしいと言われるような内容、各園で困っているような内容に近づくことができる研修を考え、開催しています。会員向けの研修会だけではなく、園長先生対象や保育現場の先生対象までターゲットを幅広く考えた研修会の開催に向けて、常に活動しています。今回は以下の3つの研修会を紹介しますが、他地域の青年部との合同研修会や社会福祉法人会計に関する研修会など、幅広い研修会を開催しているのが、青年保育者部会の特徴と言えます。また、会員にアンケート調査を行い、研修会の内容を検討する試みも行っています。
① 2024(令和6)年度は「多様性ってなんだろう? SOGI インクルーシブな環境づくり」と題し、認定特定非営利活動法人ReBitの方に講師をお願いして、多様性を尊重する保育や環境づくりを学びました。この研修会は、LGBTQ+の方々が園児や保護者であった時にどのような対応や考慮が必要なのかを知るために開催しました。既存の子育ての概念では知らず知らずのうちに、子どもや保護者を傷つけているかもしれないということを学べたと思います。
この研修会を開催するに至ったきっかけは、定例会での会話からでした。女の子の格好をしたい男の子、男の子の格好をしたい女の子をめぐって、現在の社会の中で、子どもや保護者にどのような対応、声かけができるのだろうかという会話から、実際に専門家に聞いてみようという流れになりました。そのようなアットホームな雰囲気から研修会が決まるのも、青年保育者部会の魅力であると思います。
②兵庫県行政との懇談会は、長年続いてきた青年保育者部会の勉強会です。兵庫県の担当部署の皆様から県行政の取り組みについて説明をいただき、私たちからは子育て現場での疑問点を質問することで意見交換を行ってきました。青年保育者部会だからこその和やかな雰囲気の中で、忌憚のない質問にも対応いただいて、若手保育者と県行政との距離を縮められる役割を果たしています。
実際に保育現場で子どもと触れ合う機会の多い若手保育者や、施設に一番近い各市町村行政への対応に悩んでいる会員の質問にも耳を傾けていただける機会は貴重であり、先輩方が培ってきた信頼関係があるからこそできる勉強会であると考えています。
③青年保育者部会の会員向けの研修として、施設見学を年に1回行っています。
兵庫県内の青年保育者部会会員の施設を見学する年もありましたが、2024年は東京の「まちのこども園 代々木公園」を訪問しました。参加した会員がさまざまな学びを得られるような施設見学を実施できたのではないかと考えています。他の地域へ行くことで会員同士の関係性も深まることもありますが、さまざまな施設のフィロソフィーや施設づくりに触れることで多くの学びを得られる機会になっているのではないかと感じています。
4 おわりに
摂津(せっつ)、播磨(はりま)、但馬(たじま)、丹波(たんば)、淡路(あわじ)の五国からなる兵庫県は日本列島のほぼ中央に位置し、日本で唯一、日本海と太平洋に接している県です。そのため「日本の縮図」と言われるほど多様な気候と風土、それぞれの地域で個性豊かな地域文化が根ざしています。そのような多様な地域から人が集まって意見を出し合い、情報交換を行っているため、各地域行政の対応方法、保護者や保育士確保に向けた悩みを共有していても、それぞれ違った意見が出てきます。
地域文化に加え、子どもが多い都市部から、人口減少の真っただ中にある過疎地域といった幅広い多様性を内包している青年保育者部会だからこそ、新しい発見や他地域での取り組みを自分たちで実践できる強みがあると思います。今後も、兵庫県の子育て環境の充実や発展のために、自由で楽しい雰囲気の青年保育者部会としての活動を続けてまいります。そのためには、会員の増加も目指し、皆様からのご協力とご理解を得られるような活動を続けていかなければならないと考えています。
最後になりましたが、兵庫県にはさまざまな観光地もあります。今回は、青年保育者部会の活動をお伝えしましたが、ぜひ観光地としての魅力も実感していただければと思います。豊富な魚介類をはじめ各地域の酪農品、農作物も多数あります。北と南、東と西でまったく違う魅力が詰まった地域ですので、訪れていただいた方にも多様な発見があるのではないでしょうか。ぜひ、兵庫県へ新たな魅力の発見を求め、来ていただければと思います。

研修会の様子

兵庫県行政との懇談会

定例会の様子
兵庫県保育協会青年保育者部会は、1984(昭和59)年に「青年保育者会」として発足しました。発足以降、先輩方が会議や勉強会、研修会を開催し、脈々と続いていましたが、2013(平成25)年に兵庫県保育協会が公益法人を設立した折に「青年保育者部会」と改称しました。部会となったことで、兵庫県保育協会の内部組織としての位置づけがより明確になり、活動の幅が広がりました。
発足当初より保育事業後継者の研鑽と相互の連絡協議等の活動を行うという目的で設立をされましたが、現在も青年保育者の資質向上に関する研修会の開催、会員相互の親睦や協調を密にできるような活動を行いながら若手らしい研修会も模索し、より活発な活動ができるような取り組みを考えています。
2 青年保育者部会の活動について
現在、部会長、副部会長、事務局長を中心に幹事会を開催し、青年保育者部会で行う研修会や勉強会の開催に向けての準備を行っています。また2か月に1回、定例会を開催し、会員同士の情報交流や研修会へ向けての協議を行っています。
現在の会員数が20名ほどですので、今後の活動 のためにも、会員が増えることを目指した広報活動を行う必要があると考えています。また、会員向けの研修会だけではなく、兵庫県の保育・子育て環境が充実していくような研修会も積極的に開催していきたいと思っています。
3 青年保育者部会の研修
毎年、さまざまな研修会の企画・運営を行っています。青年保育者部会らしいと言われるような内容、各園で困っているような内容に近づくことができる研修を考え、開催しています。会員向けの研修会だけではなく、園長先生対象や保育現場の先生対象までターゲットを幅広く考えた研修会の開催に向けて、常に活動しています。今回は以下の3つの研修会を紹介しますが、他地域の青年部との合同研修会や社会福祉法人会計に関する研修会など、幅広い研修会を開催しているのが、青年保育者部会の特徴と言えます。また、会員にアンケート調査を行い、研修会の内容を検討する試みも行っています。
① 2024(令和6)年度は「多様性ってなんだろう? SOGI インクルーシブな環境づくり」と題し、認定特定非営利活動法人ReBitの方に講師をお願いして、多様性を尊重する保育や環境づくりを学びました。この研修会は、LGBTQ+の方々が園児や保護者であった時にどのような対応や考慮が必要なのかを知るために開催しました。既存の子育ての概念では知らず知らずのうちに、子どもや保護者を傷つけているかもしれないということを学べたと思います。
この研修会を開催するに至ったきっかけは、定例会での会話からでした。女の子の格好をしたい男の子、男の子の格好をしたい女の子をめぐって、現在の社会の中で、子どもや保護者にどのような対応、声かけができるのだろうかという会話から、実際に専門家に聞いてみようという流れになりました。そのようなアットホームな雰囲気から研修会が決まるのも、青年保育者部会の魅力であると思います。
②兵庫県行政との懇談会は、長年続いてきた青年保育者部会の勉強会です。兵庫県の担当部署の皆様から県行政の取り組みについて説明をいただき、私たちからは子育て現場での疑問点を質問することで意見交換を行ってきました。青年保育者部会だからこその和やかな雰囲気の中で、忌憚のない質問にも対応いただいて、若手保育者と県行政との距離を縮められる役割を果たしています。
実際に保育現場で子どもと触れ合う機会の多い若手保育者や、施設に一番近い各市町村行政への対応に悩んでいる会員の質問にも耳を傾けていただける機会は貴重であり、先輩方が培ってきた信頼関係があるからこそできる勉強会であると考えています。
③青年保育者部会の会員向けの研修として、施設見学を年に1回行っています。
兵庫県内の青年保育者部会会員の施設を見学する年もありましたが、2024年は東京の「まちのこども園 代々木公園」を訪問しました。参加した会員がさまざまな学びを得られるような施設見学を実施できたのではないかと考えています。他の地域へ行くことで会員同士の関係性も深まることもありますが、さまざまな施設のフィロソフィーや施設づくりに触れることで多くの学びを得られる機会になっているのではないかと感じています。
4 おわりに
摂津(せっつ)、播磨(はりま)、但馬(たじま)、丹波(たんば)、淡路(あわじ)の五国からなる兵庫県は日本列島のほぼ中央に位置し、日本で唯一、日本海と太平洋に接している県です。そのため「日本の縮図」と言われるほど多様な気候と風土、それぞれの地域で個性豊かな地域文化が根ざしています。そのような多様な地域から人が集まって意見を出し合い、情報交換を行っているため、各地域行政の対応方法、保護者や保育士確保に向けた悩みを共有していても、それぞれ違った意見が出てきます。
地域文化に加え、子どもが多い都市部から、人口減少の真っただ中にある過疎地域といった幅広い多様性を内包している青年保育者部会だからこそ、新しい発見や他地域での取り組みを自分たちで実践できる強みがあると思います。今後も、兵庫県の子育て環境の充実や発展のために、自由で楽しい雰囲気の青年保育者部会としての活動を続けてまいります。そのためには、会員の増加も目指し、皆様からのご協力とご理解を得られるような活動を続けていかなければならないと考えています。
最後になりましたが、兵庫県にはさまざまな観光地もあります。今回は、青年保育者部会の活動をお伝えしましたが、ぜひ観光地としての魅力も実感していただければと思います。豊富な魚介類をはじめ各地域の酪農品、農作物も多数あります。北と南、東と西でまったく違う魅力が詰まった地域ですので、訪れていただいた方にも多様な発見があるのではないでしょうか。ぜひ、兵庫県へ新たな魅力の発見を求め、来ていただければと思います。
(三浦義崇/兵庫県保育協会青年保育者部会部会長)

研修会の様子

兵庫県行政との懇談会

定例会の様子
Report
2025.06.05
全私保連青年会議 令和6年度の振り返りとこれから
こども家庭庁の発足から2年目を迎えた令和6年度。こども誰でも通園制度や保育士配置基準の見直し、児童手当の拡充など、子どもを社会の中心に据えた政策が次々と打ち出され、まさに「こどもまんなか社会」の実現に向けた本格的な転換期となりました。私たち全私保連青年会議にとっても、自分たちの存在意義をあらためて見つめ直し、新しい一歩を踏み出す年となりました。
令和6年度を振り返ると、青年会議がこれま で築いてきた信頼関係と団結力を土台にしながら、新たな挑戦を積極的に行った1年間であったと感じています。
この大会では、参加人数の多さに加え、お招きした講師陣の豪華な顔ぶれや内容の濃さ、東京という立地を活かした分科会の構成が光り、「非常に満足した」との声が数多く寄せられました。情報交換会も満席となり、全国各地から集まった保育関係者が地域や立場を越えて親睦を深める様子が見られました。改めて、保育を志す者同士がつながり合う場の重要性を実感した大会でもありました。
2025年2月に開催した特別セミナーでは、「承継─自分たちの手で決める」というテーマの下、事業承継に焦点を当てた鼎談形式での研修がメインでした。
これからの園経営において避けては通れないテーマに対して、実際に承継を経験された先生たちのリアルな声を共有し、多くの参加者が自身の未来像を重ね合わせる時間となりました。2日目の記念講演には、(株)八天堂社長・森光孝雅氏をお迎えし、企業としての歩みやご自身の経験、そして次世代への事業承継について語っていただきました。実体験に基づいた講演内容は、保育とは異なる分野でありながらも多くの共通点を感じることができ、大変学びの深い時間でした。
そして令和6年度に初めて実現した、日本保育 協会青年部との合同研修会。令和6年能登半島地震のチャリティー研修として位置づけた本研修会には、(株)保育システム研究所代表・吉田正幸氏、接客向上委員会&Peace 代表・石坂秀己氏という素晴らしい講師をお迎えしました。お二方とも「保育界の若手を応援したい」「被災地の力になりたい」と、講演料寄付のご協力を快く引き受けてくださいました。
講演の内容も非常に実践的かつ熱量の高いもので、参加者の心に強く残る研修となりました。
また、各部会の活動も着実に前に進んでいます。総務部、企画部、調査研究部、研修部、広報部、それぞれの部会が、これまで先輩方が紡いできたものを大切にしつつ、今の時代に即した取り組みに挑戦しています。さらに、各部会に求められていることを敏感に察知し、スピード感を持って「形」にしていく、そんな姿勢がますます重要になっていると感じています。部を越えて連携し合いながら、よりよい青年会議を創り上げていきたいと思います。
最後に、これからの青年会議について。若さというのは大きな武器だと思っています。感覚、感性、瞬発力、行動力、吸収力などは、若手ならではの強みであると感じます。それらを十分に発揮しつつ、諸先輩方の経験や知見もお借りして、自分たちらしく、子どもたちのために、仲間とともに進んでまいります。
今後とも、全私保連青年会議への変わらぬご支援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
伊藤悟青年会議会長

特別セミナーの様子

日保協青年部との合同研修会にて

令和6年度第4回幹事会(2025年2月13日)

↑青年会議 Instagram アプリをお持ちの方はここから閲覧できます。
令和6年度を振り返ると、青年会議がこれま で築いてきた信頼関係と団結力を土台にしながら、新たな挑戦を積極的に行った1年間であったと感じています。
* * *
まずは、2024年9月に京王プラザホテルにて開催した東京大会。800名もの方々に参加いただいたこの大会は、過去最大規模となりました。大会のテーマは「CORE─こどもたち、ど真ん中」。私たちが大切にしたい価値観の「核」に、もう一度立ち返る機会となるよう願いを込めて企画しました。実行委員を中心に、全国の仲間たちが力を合わせ、本当に多くの関係者が関わり、青年会議らしさが溢れる大会を実現することができました。この大会では、参加人数の多さに加え、お招きした講師陣の豪華な顔ぶれや内容の濃さ、東京という立地を活かした分科会の構成が光り、「非常に満足した」との声が数多く寄せられました。情報交換会も満席となり、全国各地から集まった保育関係者が地域や立場を越えて親睦を深める様子が見られました。改めて、保育を志す者同士がつながり合う場の重要性を実感した大会でもありました。
2025年2月に開催した特別セミナーでは、「承継─自分たちの手で決める」というテーマの下、事業承継に焦点を当てた鼎談形式での研修がメインでした。
これからの園経営において避けては通れないテーマに対して、実際に承継を経験された先生たちのリアルな声を共有し、多くの参加者が自身の未来像を重ね合わせる時間となりました。2日目の記念講演には、(株)八天堂社長・森光孝雅氏をお迎えし、企業としての歩みやご自身の経験、そして次世代への事業承継について語っていただきました。実体験に基づいた講演内容は、保育とは異なる分野でありながらも多くの共通点を感じることができ、大変学びの深い時間でした。
そして令和6年度に初めて実現した、日本保育 協会青年部との合同研修会。令和6年能登半島地震のチャリティー研修として位置づけた本研修会には、(株)保育システム研究所代表・吉田正幸氏、接客向上委員会&Peace 代表・石坂秀己氏という素晴らしい講師をお迎えしました。お二方とも「保育界の若手を応援したい」「被災地の力になりたい」と、講演料寄付のご協力を快く引き受けてくださいました。
講演の内容も非常に実践的かつ熱量の高いもので、参加者の心に強く残る研修となりました。
* * *
研修以外では、新たな取り組みとして Instagramの公式アカウントを開設し、少しずつ情報発信を開始しています。「保育をもっと身近に、青年会議をもっと身近に感じてもらいたい」という思いを込めて運営しています。先にも述べた研修会の様子や、私たち青年会議のリアルな活動などを、画像や動画を通して発信することで、一人でも多くの方に保育の魅力を知っていただければと考えています。今後はさらに力を入れ、全国の仲間とつながる広報ツールとして活用していきたいと考えています。また、各部会の活動も着実に前に進んでいます。総務部、企画部、調査研究部、研修部、広報部、それぞれの部会が、これまで先輩方が紡いできたものを大切にしつつ、今の時代に即した取り組みに挑戦しています。さらに、各部会に求められていることを敏感に察知し、スピード感を持って「形」にしていく、そんな姿勢がますます重要になっていると感じています。部を越えて連携し合いながら、よりよい青年会議を創り上げていきたいと思います。
* * *
私たちがこうして全国で活動できているのは 、全私保連会員園の皆様の後押しや、日々の調整、連絡、資料作成に至るまで、裏方で奔走してくださっている事務局の方々の支えがあってのものです。心から感謝申し上げます。また、私たちが園を離れて活動している間、現場を守り、子どもたちと向き合ってくださっている先生たちの存在がなければ、青年会議の活動は成り立ちません。全国で日々奮闘されている保育者の皆様、本当にありがとうございます。最後に、これからの青年会議について。若さというのは大きな武器だと思っています。感覚、感性、瞬発力、行動力、吸収力などは、若手ならではの強みであると感じます。それらを十分に発揮しつつ、諸先輩方の経験や知見もお借りして、自分たちらしく、子どもたちのために、仲間とともに進んでまいります。
今後とも、全私保連青年会議への変わらぬご支援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
(伊藤 悟/全私保連青年会議会長)

伊藤悟青年会議会長

特別セミナーの様子

日保協青年部との合同研修会にて

令和6年度第4回幹事会(2025年2月13日)

↑青年会議 Instagram アプリをお持ちの方はここから閲覧できます。
Report
2025.05.08
北九州市私立保育連盟青年会議の紹介
1 北九州市の魅力
北九州市は、九州の玄関口として多彩な魅力をもつ都市です。日本有数のカルスト台地や鍾乳洞を有する平尾台、カブトガニなど希少生物の宝庫である曽根干潟など、多彩で豊かな自然環境が広がっています。また、観光地としても有名な門司港レトロ地区は、明治から昭和初期にかけて建築された趣のある建物が今も残り、散策しながら歴史を感じることができます。さらに、豊前海一粒(びぜんkかいひとつぶ)かきや小倉牛 、合馬(おうま)のたけのこなど、魅力的な海の幸・山の幸が溢れています。交通インフラも充実しており、新幹線、フェリー、北九州空港を利用した遠方とのアクセスも大変便利です。
北九州市は自然と都市が調和し、歴史と文化が 息づく魅力的な都市です。ぜひ、一度訪れて、その多彩な魅力を体感してみてください。
2 青年会議の活動
青年会議会長・事務局・会計を中心に総務部・ 調査研究部・広報部に分かれ、さまざまな取り組みを行っています。主な活動は以下の通りです。
(1) 各種研修会の開催および関係組織研修会への参加
(2) 市議会議員・保育行政との勉強会
(3) 北九州市私立保育連盟事業への参加
(4) 調査研究活動
(5) 青年会議活動の情報発信
(6) その他必要事業等
① 総務部
北九州市私立保育連盟青年会議の活動を、一人でも多くの方に知っていただくとともに、園運営や保育における資質向上を目指し、研鑽を積むことのできる研修会等を行っています。
具体的には、北九州市私立保育連盟の加盟園を対象にした青年会議独自研修会の開催や、北九州市行政との勉強会や意見交換会、北九州市議会議員との意見交換会および交流会、他都市との合同研修会等の企画・立案などの活動を行っています。
② 調査研究部
北九州市私立保育連盟の調査・研修委員会と連携、協力しながら、会員の知りたい情報や必要な情報を調査研究していくとともに、青年会議独自の調査研究を行っていくことで、行政や市議会議員との勉強会の際の下地になり得る調査研究を行ってい ます。また、他都市との研修交流会を通して青年会議独自の情報収集を行っています。
③ 広報部
会報『青空通信』の発行、並びに私保連青年会議ホームページを積極的に活用し、青年会議活動の報告・情報発信を行っています。主な内容としては、『青空通信』を年1回発行し、研修報告、活動報告、調査研究報告等を掲載、私保連青年会議ホームページを利用して、保育関係者や社会に向けて新しい情報を発信しています。その他、研修活動等の記録を行うとともに、新たな広報活動を模索・推進していく活動を担っています。
3 青年会議独自の研修会と取り組み
青年会議が毎年必ず行う研修会の中に、運動会種目研修会があります。北九州市私立保育連盟の加盟園を対象に開催を続け、初めは少なかった参加者も今ではすぐに定員いっぱいになる研修会となり、ブラッシュアップさせていきながら続けることの大切さを感じます。
さらに、歴代の諸先輩方が築いてくださった保育行政、市議会議員と青年会議との勉強会や意見交換会も今では大変重要な機会となっています。また、青年会議ならではの活発な意見交換がもととなり、北九州市私立保育連盟からの要望である「より良い施設運営」につながっていくという好事例も生じたことはとても嬉しく、青年会議メンバーの今後のやりがいにもつながっています。
そして、“我ら福岡”が誇る取り組みとして、「北九州市・福岡県・福岡市:福岡保育三社会」の合同研修会があります。1年ごとに各市・県組織の持ち回りで、その時々に合わせたタイムリーな内容での研修会を行っています。持ち回りのため、それぞれの組織で気になることや知りたいことなど、違う組織だからこその気づきや学びが多くあり、地元組織だけで行う研修会とはまったく違った良い学びの場となっています。
また、研修会終了後の懇親会では“福岡らしさ”全開の交流ができて、これからの難しい施設運営の舵取りを行っていく私たち青年会議にとって、とても有意義な時間となっています。
4 青年会議のこれから
今後も、地元組織に限らずさまざまな組織の方々との交流を広め、絆を深めていくことで、それぞれの組織の青年会議が新しい思考や気づきを得て、さらに自身の法人(組織)を守っていくヒントや行動につながっていく多角的な視点をもつことができるようにしていければと思います。
明日の保育を担う私たち青年会議は、「保育 は北九州から」の気概と一枚岩の結束力をもって、若者らしい斬新な発想力と果敢な行動力を発揮していくことができるよう活動を続けていきます。
引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

青年会議独自の研修会「運動指導者研修会」の様子
(2023年7月)

青年会議独自の研修会 「指導者LaQ研修会」の様子
(2024年2月)

北九州市・福岡県・福岡市:福岡保育三社会の合同研修会の様子(2024年2月)

合同研修会の参加メンバー
北九州市は、九州の玄関口として多彩な魅力をもつ都市です。日本有数のカルスト台地や鍾乳洞を有する平尾台、カブトガニなど希少生物の宝庫である曽根干潟など、多彩で豊かな自然環境が広がっています。また、観光地としても有名な門司港レトロ地区は、明治から昭和初期にかけて建築された趣のある建物が今も残り、散策しながら歴史を感じることができます。さらに、豊前海一粒(びぜんkかいひとつぶ)かきや小倉牛 、合馬(おうま)のたけのこなど、魅力的な海の幸・山の幸が溢れています。交通インフラも充実しており、新幹線、フェリー、北九州空港を利用した遠方とのアクセスも大変便利です。
北九州市は自然と都市が調和し、歴史と文化が 息づく魅力的な都市です。ぜひ、一度訪れて、その多彩な魅力を体感してみてください。
2 青年会議の活動
青年会議会長・事務局・会計を中心に総務部・ 調査研究部・広報部に分かれ、さまざまな取り組みを行っています。主な活動は以下の通りです。
(1) 各種研修会の開催および関係組織研修会への参加
(2) 市議会議員・保育行政との勉強会
(3) 北九州市私立保育連盟事業への参加
(4) 調査研究活動
(5) 青年会議活動の情報発信
(6) その他必要事業等
① 総務部
北九州市私立保育連盟青年会議の活動を、一人でも多くの方に知っていただくとともに、園運営や保育における資質向上を目指し、研鑽を積むことのできる研修会等を行っています。
具体的には、北九州市私立保育連盟の加盟園を対象にした青年会議独自研修会の開催や、北九州市行政との勉強会や意見交換会、北九州市議会議員との意見交換会および交流会、他都市との合同研修会等の企画・立案などの活動を行っています。
② 調査研究部
北九州市私立保育連盟の調査・研修委員会と連携、協力しながら、会員の知りたい情報や必要な情報を調査研究していくとともに、青年会議独自の調査研究を行っていくことで、行政や市議会議員との勉強会の際の下地になり得る調査研究を行ってい ます。また、他都市との研修交流会を通して青年会議独自の情報収集を行っています。
③ 広報部
会報『青空通信』の発行、並びに私保連青年会議ホームページを積極的に活用し、青年会議活動の報告・情報発信を行っています。主な内容としては、『青空通信』を年1回発行し、研修報告、活動報告、調査研究報告等を掲載、私保連青年会議ホームページを利用して、保育関係者や社会に向けて新しい情報を発信しています。その他、研修活動等の記録を行うとともに、新たな広報活動を模索・推進していく活動を担っています。
3 青年会議独自の研修会と取り組み
青年会議が毎年必ず行う研修会の中に、運動会種目研修会があります。北九州市私立保育連盟の加盟園を対象に開催を続け、初めは少なかった参加者も今ではすぐに定員いっぱいになる研修会となり、ブラッシュアップさせていきながら続けることの大切さを感じます。
さらに、歴代の諸先輩方が築いてくださった保育行政、市議会議員と青年会議との勉強会や意見交換会も今では大変重要な機会となっています。また、青年会議ならではの活発な意見交換がもととなり、北九州市私立保育連盟からの要望である「より良い施設運営」につながっていくという好事例も生じたことはとても嬉しく、青年会議メンバーの今後のやりがいにもつながっています。
そして、“我ら福岡”が誇る取り組みとして、「北九州市・福岡県・福岡市:福岡保育三社会」の合同研修会があります。1年ごとに各市・県組織の持ち回りで、その時々に合わせたタイムリーな内容での研修会を行っています。持ち回りのため、それぞれの組織で気になることや知りたいことなど、違う組織だからこその気づきや学びが多くあり、地元組織だけで行う研修会とはまったく違った良い学びの場となっています。
また、研修会終了後の懇親会では“福岡らしさ”全開の交流ができて、これからの難しい施設運営の舵取りを行っていく私たち青年会議にとって、とても有意義な時間となっています。
4 青年会議のこれから
今後も、地元組織に限らずさまざまな組織の方々との交流を広め、絆を深めていくことで、それぞれの組織の青年会議が新しい思考や気づきを得て、さらに自身の法人(組織)を守っていくヒントや行動につながっていく多角的な視点をもつことができるようにしていければと思います。
明日の保育を担う私たち青年会議は、「保育 は北九州から」の気概と一枚岩の結束力をもって、若者らしい斬新な発想力と果敢な行動力を発揮していくことができるよう活動を続けていきます。
引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。
(宮原健輔/北九州市私立保育連盟青年会議会長、認定こども園栄美保育園園長)

青年会議独自の研修会「運動指導者研修会」の様子
(2023年7月)

青年会議独自の研修会 「指導者LaQ研修会」の様子
(2024年2月)

北九州市・福岡県・福岡市:福岡保育三社会の合同研修会の様子(2024年2月)

合同研修会の参加メンバー
Report
2025.04.07
第18回青年会議特別セミナー開催報告
2月13日~14日、第18回青年会議特別セミナーが東京・浅草ビューホテルにて開催されました。
「承継~自分たちの手で決める~」というテーマの下で、全国各地より159名の先生方にご参加いただきました。当日は急な電車の遅延等のトラブルもありましたが、皆様のご協力の下、成功裏に終えることができました。今回の青年会議掲示板では、セミナーの様子についてご紹介します。
■1日目(2月13日)
【開会】
開会にあたり、伊藤青年会議会長より「『こどもまんなか社会』と言いつつも、子どもの数が少ない現状。我々運営する立場も本気で危機感を持っていかなければいけないフェーズに入っている。本セミナーではきっと、これからの経営のヒントになる話が聞けると思う」という挨拶がありました。テーマからも、会長の思いや青年会議の決意や覚悟といったものが伝わってきます。
昨年に引き続き、インパクトのあるテーマの下、参加者の熱意と期待に溢れる雰囲気の中で、本年の特別セミナーが幕を開けました。
【情勢報告】
齊藤全私保連常務理事より、最新の保育関係情勢についてご報告いただきました。
人口動態や実態調査の結果等の最新情報に加え、ご自身の見解や分析も交えながらの詳細な説明がなされ、参加者に理解しやすい形で報告いただきました。保育の量の拡充から持続可能でより質の高い保育の時代に向け、私たち保育関係者が理解しておくべき情報や視点について示していただき、終盤には保育三団体の要望が国に着実に反映されている実態も鑑み、現場から声を上げ続けていくことの大切さも訴えられました。最新情報を知るとともに、明日からの保育を考える情勢報告でした。
【講演】
保育業界の現状と潮流
講師:大嶽広展氏・(株)カタグルマ代表取締役
続いて行われた保育業界向けSaas企画・開発・研究・運営等で知られる(株)カタグルマの大嶽氏による講演は、市場ニーズと需給バランスの観点に始まり、独自の分析と保育の実態も踏まえた、経営サイド視点に重きを置いたお話が展開されました。
刻一刻と変化していく社会情勢において、我々保育者にとっては少子高齢化によるさまざまな影響があり、今後もその流れが継続していくことは想像に難くありません。将来を見据えた拡大・維持・縮小それぞれの成長シナリオの決断について考えていかなければならないことに気づかされる内容に、心動かされた方も多かったのではないでしょうか。地域になくてはならない選ばれる園、そしてこれからは地域社会をつくる存在となっていくことの重要性も再認識させられました。一味違った視点や鋭い切り口からの講演に、参加者は「今何ができるのか?自分たちは何をすべきなのか?」と覚悟を問われ、非常に考えさせられた時間となりました。
【パネルディスカッション】
自分たちの手で決める
〈パネリスト〉
織田義政氏・(社福)大治東福祉会理事長
伊藤直樹氏・(社福)田川保育会田川保育園施設長有松徹氏・(社福)ヒトトナリ理事長
〈コーディネーター〉
龍山浄氏・(社福)伴福祉会とも認定こども園副園長
それぞれが多職種・他業界から保育業界に足を踏み入れた経歴を持ち、自らの組織運営に加え、地方組織・全国組織でも活躍中の3名によるパネルディスカッションが展開されました。本セミナーのサブタイトル「自分たちの手で決める」をテーマに、忌憚のない意見交換がなされ、跡継ぎ、世代交換等の事業承継という難題について、三者三様の想いがステージ上で飛び交いました。
まず、先代から承継時のそれぞれの背景・思考・想いの違いなどから生じた課題やその際の苦労話などが語られました。そして、課題解決のための方法や課題への向き合い方、さらには、次代への継承をどう考えるかといった将来を見据えたより具体的な方策まで、非常に内容の濃いリアルな語り合いが行われました。事業継承に際し、どんな選択をしても、そこにはそれぞれの背景・価値観があり、その想いを活かしていくことの大切さも感じられました。
誰にも訪れる「自分で決める」承継の時、今回のお話がきっと大きな力で後押ししてくれる、バイタリティーに溢れたパネルディスカッションでした。
■2日目(2月14日)
【記念講演】
継往開来
講師:森光孝雅氏・(株)八天堂代表取締役
2日目の記念講演は、「くりーむパン」で全国的に有名な八天堂の森光氏に講演をいただきました。
今日の八天堂に至るまでの紆余曲折の歩みや、自身の経験談をもとに経営者としての心構えや組織のトップとしての姿勢・あり方などを力強く語っていただきました。
「事を成すは逆境にあり。事を破るは順境にあり」苦境の時こそ前を向き打開策を講じ、順境の時こそ現状に甘んじることなく常に前を向く。まずこの言葉に心を打たれました。そして「現状維持は退化である」など、考えさせれられる言葉は枚挙に遑がありません。
日々変化する社会情勢に加えて、私たち経営者の周辺の状況も刻一刻と変化していきます。激動の時代の中、事業をより良いものにしていくために覚悟を決めていく必要があり、事業承継の難しさや大切さを改めて痛感した講演でした。
今回の青年会議特別セミナーは「承継」をメインテーマに開催しました。似た意味をもつ継承に比べ耳慣れない言葉ですが、精神・理念・思想などの思いの部分を継ぐ意味合いを重視したいと青年会議内で議論を重ね、テーマを設定し、そうした考えや想いを重視した講演やパネルディスカッション等を展開していきました。改めて、参加者の皆様のこれからの事業における承継はどうあるべきかを考えるヒントになっていたなら幸いです。
今回も多くの皆様にご参加をいただき、誠にありがとうございました。青年会議は今後も「らしさ」を忘れず、新たな視点を模索し続けていきたいと思います。

パネルディスカッションの様子
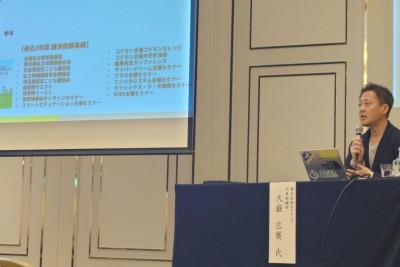
大嶽広展氏

森光孝雅氏

セミナーの会場
「承継~自分たちの手で決める~」というテーマの下で、全国各地より159名の先生方にご参加いただきました。当日は急な電車の遅延等のトラブルもありましたが、皆様のご協力の下、成功裏に終えることができました。今回の青年会議掲示板では、セミナーの様子についてご紹介します。
■1日目(2月13日)
【開会】
開会にあたり、伊藤青年会議会長より「『こどもまんなか社会』と言いつつも、子どもの数が少ない現状。我々運営する立場も本気で危機感を持っていかなければいけないフェーズに入っている。本セミナーではきっと、これからの経営のヒントになる話が聞けると思う」という挨拶がありました。テーマからも、会長の思いや青年会議の決意や覚悟といったものが伝わってきます。
昨年に引き続き、インパクトのあるテーマの下、参加者の熱意と期待に溢れる雰囲気の中で、本年の特別セミナーが幕を開けました。
【情勢報告】
齊藤全私保連常務理事より、最新の保育関係情勢についてご報告いただきました。
人口動態や実態調査の結果等の最新情報に加え、ご自身の見解や分析も交えながらの詳細な説明がなされ、参加者に理解しやすい形で報告いただきました。保育の量の拡充から持続可能でより質の高い保育の時代に向け、私たち保育関係者が理解しておくべき情報や視点について示していただき、終盤には保育三団体の要望が国に着実に反映されている実態も鑑み、現場から声を上げ続けていくことの大切さも訴えられました。最新情報を知るとともに、明日からの保育を考える情勢報告でした。
【講演】
保育業界の現状と潮流
講師:大嶽広展氏・(株)カタグルマ代表取締役
続いて行われた保育業界向けSaas企画・開発・研究・運営等で知られる(株)カタグルマの大嶽氏による講演は、市場ニーズと需給バランスの観点に始まり、独自の分析と保育の実態も踏まえた、経営サイド視点に重きを置いたお話が展開されました。
刻一刻と変化していく社会情勢において、我々保育者にとっては少子高齢化によるさまざまな影響があり、今後もその流れが継続していくことは想像に難くありません。将来を見据えた拡大・維持・縮小それぞれの成長シナリオの決断について考えていかなければならないことに気づかされる内容に、心動かされた方も多かったのではないでしょうか。地域になくてはならない選ばれる園、そしてこれからは地域社会をつくる存在となっていくことの重要性も再認識させられました。一味違った視点や鋭い切り口からの講演に、参加者は「今何ができるのか?自分たちは何をすべきなのか?」と覚悟を問われ、非常に考えさせられた時間となりました。
【パネルディスカッション】
自分たちの手で決める
〈パネリスト〉
織田義政氏・(社福)大治東福祉会理事長
伊藤直樹氏・(社福)田川保育会田川保育園施設長有松徹氏・(社福)ヒトトナリ理事長
〈コーディネーター〉
龍山浄氏・(社福)伴福祉会とも認定こども園副園長
それぞれが多職種・他業界から保育業界に足を踏み入れた経歴を持ち、自らの組織運営に加え、地方組織・全国組織でも活躍中の3名によるパネルディスカッションが展開されました。本セミナーのサブタイトル「自分たちの手で決める」をテーマに、忌憚のない意見交換がなされ、跡継ぎ、世代交換等の事業承継という難題について、三者三様の想いがステージ上で飛び交いました。
まず、先代から承継時のそれぞれの背景・思考・想いの違いなどから生じた課題やその際の苦労話などが語られました。そして、課題解決のための方法や課題への向き合い方、さらには、次代への継承をどう考えるかといった将来を見据えたより具体的な方策まで、非常に内容の濃いリアルな語り合いが行われました。事業継承に際し、どんな選択をしても、そこにはそれぞれの背景・価値観があり、その想いを活かしていくことの大切さも感じられました。
誰にも訪れる「自分で決める」承継の時、今回のお話がきっと大きな力で後押ししてくれる、バイタリティーに溢れたパネルディスカッションでした。
■2日目(2月14日)
【記念講演】
継往開来
講師:森光孝雅氏・(株)八天堂代表取締役
2日目の記念講演は、「くりーむパン」で全国的に有名な八天堂の森光氏に講演をいただきました。
今日の八天堂に至るまでの紆余曲折の歩みや、自身の経験談をもとに経営者としての心構えや組織のトップとしての姿勢・あり方などを力強く語っていただきました。
「事を成すは逆境にあり。事を破るは順境にあり」苦境の時こそ前を向き打開策を講じ、順境の時こそ現状に甘んじることなく常に前を向く。まずこの言葉に心を打たれました。そして「現状維持は退化である」など、考えさせれられる言葉は枚挙に遑がありません。
日々変化する社会情勢に加えて、私たち経営者の周辺の状況も刻一刻と変化していきます。激動の時代の中、事業をより良いものにしていくために覚悟を決めていく必要があり、事業承継の難しさや大切さを改めて痛感した講演でした。
今回の青年会議特別セミナーは「承継」をメインテーマに開催しました。似た意味をもつ継承に比べ耳慣れない言葉ですが、精神・理念・思想などの思いの部分を継ぐ意味合いを重視したいと青年会議内で議論を重ね、テーマを設定し、そうした考えや想いを重視した講演やパネルディスカッション等を展開していきました。改めて、参加者の皆様のこれからの事業における承継はどうあるべきかを考えるヒントになっていたなら幸いです。
今回も多くの皆様にご参加をいただき、誠にありがとうございました。青年会議は今後も「らしさ」を忘れず、新たな視点を模索し続けていきたいと思います。
(伊藤隆将/全私保連青年会議広報部)

パネルディスカッションの様子
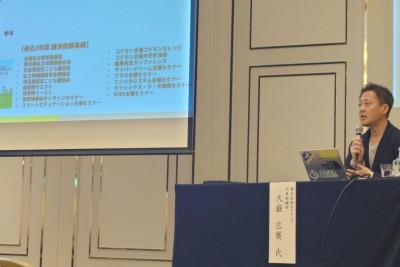
大嶽広展氏

森光孝雅氏

セミナーの会場
■第1日目
【オープニングアクト】
奄美の名瀬を舞台に活動をされているあらしゃげ会に、八月踊りを披露してもらいました。八月踊りは旧暦8月の祭事に奄美の各集落で五穀豊穣や厄除けを願って行われる、奄美の伝統的な踊りです。
【開会式】
川畑鉄平副実行委員長による開会宣言で開会式が始まり、友岡善信実行委員長から開催地挨拶、川下勝利全私保連会長、伊藤悟全私保連青年会議会長から主催挨拶がなされました。来賓挨拶では、安田壮平様(奄美市長)、中西淳也様(日本保育協会青年部部長)よりご挨拶をいただきました。
【パネルディスカッション】
離島~ク Talk─離島の魅力や課題を知る
パネリストとして林田登志子氏(長崎県五島市)、櫻井真美氏(東京都大島町)、川東敬氏(鹿児島県屋久島町)、コーディネーターとして鹿児島県保育連合会副会長・下園和靖氏(鹿児島県南さつま市)に登壇いただき、多様な離島の魅力を掘り下げるとともに、それぞれの地域が抱える課題に対しての取り組み等について議論を深めました。
【分科会】
アマホームPLAZAで第1~3分科会、第4~5分科会はフィールドワークを開催しました。申し込み開始すぐに定員に達する分科会もあり、分科会全体を通して好評をいただきました。
● 第1分科会(定員 120 名)
地域資源を活用した園づくり
─地域とともに子どもたちの未来をつむぐ
講師:坂本喜一郎氏(RISSHO KID'S きらり園長)
地域の人・自然・文化を教育資源として活かし、子どもたちが地域に誇りと愛着をもって育つための実践が紹介されました。特に、園が地域とともに成長するという視点は、今後の保育経営にも重要な示唆を与えてくださいました。
● 第2分科会(定員 80 名)
子どもの発達から考える保育環境
─園内の資源を活かして魅力ある保育環境づくり
講師:大方美香氏(大阪総合保育大学学長・教授)
発達段階に応じた環境構成の大切さや、子どもの主体的な活動を支える保育者の関わり方について具体的な実践を交えて解説いただき、改めて「環境が子どもを育てる」という言葉の重みを感じました。
● 第3分科会(定員 40 名)
絵本とその読み聞かせ
─読み聞かせの意義と奄美民話
講師:余郷裕次氏(鳴門教育大学大学院教授) ・嘉原カヲリ氏(あまみ子どもライブラリー)
嘉原氏からは地域の風土や自然環境が子どもの育ちに与える影響について学び、余郷氏からは絵本を通じて心の豊かさや想像力を育む意義を再認識しました。
● 第4分科会(定員 20 名)フィールドワーク①
金井工芸
泥染め体験─泥遊びと泥染め体験
自然の素材を用いた染め物作りを通して、奄美の伝統文化に触れることができました。また、保育でも「本物に触れる体験」の価値を再確認しました。
● 第5分科会(定員 40 名)フィールドワーク②
黒潮の森マングローブパーク
マングローブ散策
─自然体験とマングローブの森散策
カヌーでのマングローブ散策を実施し、自然の壮大さと生命の営みを肌で感じることができました。
【情報交換会】
夕刻から、第1会場・ホテルサンデイズ奄美(鶏飯・郷土料理「愛かな」)、第2会場・奄美山羊島ホテルで情報交換会を開催しました。
開式の乾杯までは開場をzoomでつなぎ、その後は各会場で情報交換会を行いました。第1会場では指笛講座、徳之島出身のアーティスト・城朋仁氏によるライブ演奏、第2会場では奄美出身の楠田莉子氏、平田まりな氏による民謡ライブが行われました。
保育運動推進会議より新保育運動、次回開催の全国私立保育研究大会北九州大会実行委員会、青年会議全国大会岩手大会実行委員会の皆様にPRを行っていただき、奄美の食や文化を堪能しながらのとても賑やかな情報交換会となりました。
■第2日目
【情勢報告】
齊藤勝全私保連常務理事より、保育を取り巻く情勢についての報告がなされました。
【記念講演(対談)】
心豊かに生きる力が育つまちづくり
─島に学ぶ、生きる力が育つ魅力的な子育て環境
離島の豊かな自然と文化の中で育まれる「生きる力」について、鯨本あつこ氏(離島経済新聞社代表理事)、岡野亜湖氏(「クヮマガつむぐ会」代表)のお二人の視点から深く語り合っていただきました。
【閉会式】
友岡善信実行委員長、吉岡崇全私保連青年会議副会長、次回開催の岩手大会・福島大輔実行委員長に挨拶をいただき、川元健副実行委員長による閉会宣言で、2日間のプログラムに幕が降ろされました。
* * *
青年会議全国大会を鹿児島県・奄美大島で開催することが決定してから、鹿児島県子ども子育て青年会を中心に鹿児島本土、屋久島、奄美群島の会員で実行委員会を組織し準備を進めてきました。約2年間で現地調査、東京大会視察、定例会議等、活動を活発に行ってきました。そして多くの関係各位の皆様に協力をいただいたことで、奄美大会を無事に開催することができたこと、何よりも嬉しく思います。
次回の岩手大会では、福島大輔実行委員長を中心に準備をされています。岩手で初の青年会議全国大会が盛大に開催されることを心から願っています。大会数日前に台風や豪雨の予報が出ており、大会 の開催、交通面等で心配されました。しかし、会期中に雨が降ることはありましたが、大きな事故やトラブルもなく、成功裡に終えることができました。第44回全私保連青年会議奄美大会にご協力いただいた関係各位の皆様に、深く御礼申し上げます。
開会式
パネルディスカッション
記念講演(対談)
分科会の様子
フィールドワーク②